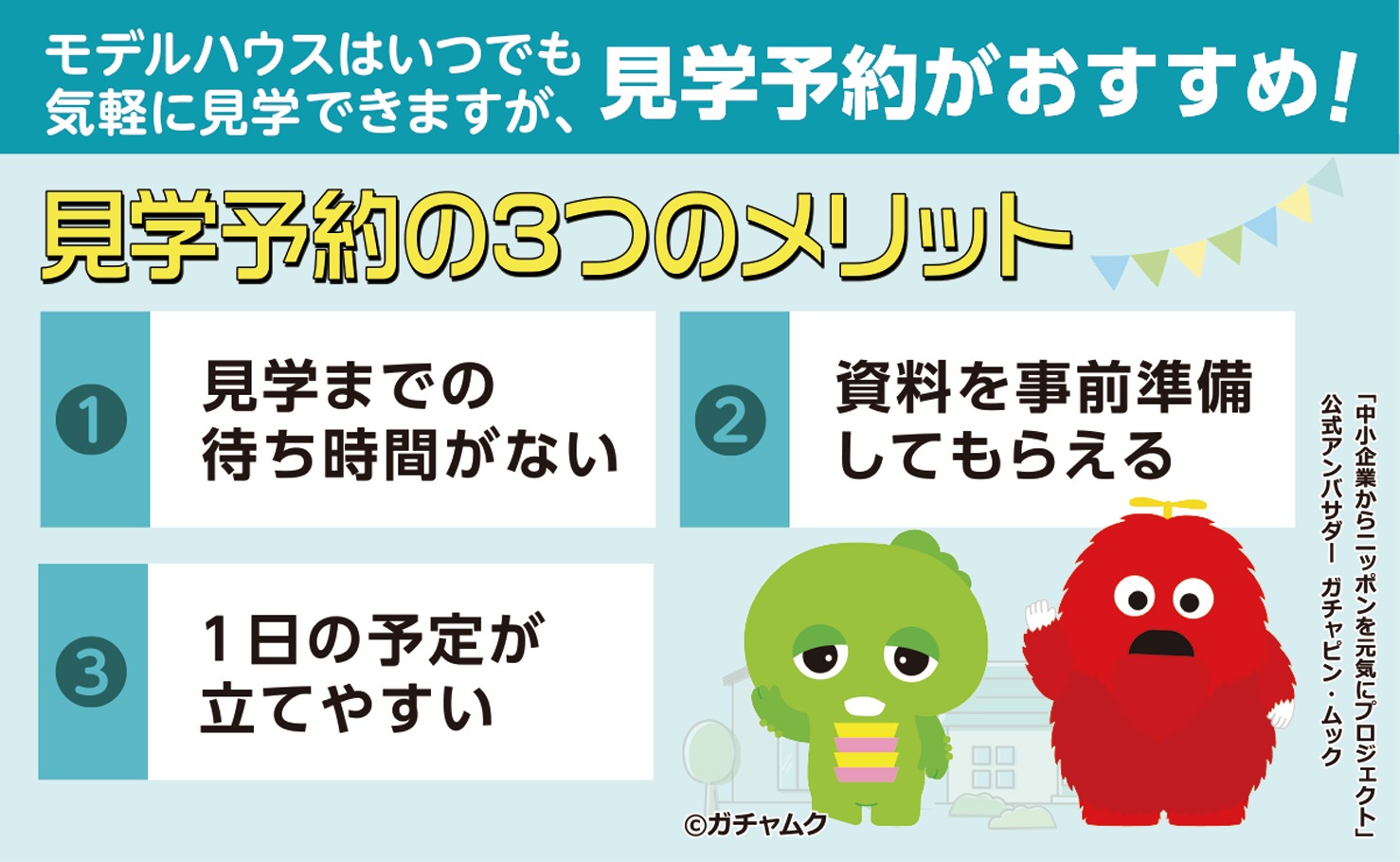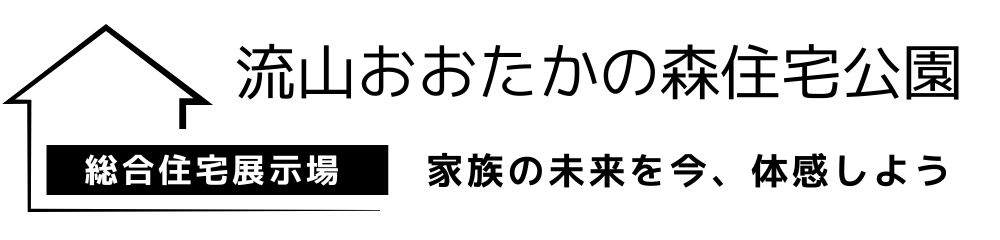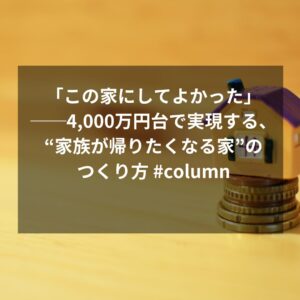この記事を読めば分かること
- 「坪単価60万円」の表面に隠された、本当の住宅コストとは?
- 家の構造でなぜここまで費用差が出るのか?
- 「この価格で建ちます」に含まれていない、重要な“暮らすための費用”とは?
- 注文住宅を建てる前に必ず押さえたい、費用の3層構造
- 予算オーバーしないための“逆算式”家づくりのはじめ方
はじめに
「この家、坪単価は約60万円ですね」
営業マンのこの一言に、あなたの目の奥がキラリと反応する。
予算内かも――そんな期待がふくらむ瞬間。
でも、ちょっと待ってください。
その“坪単価”、本当にそのまま信じていいのでしょうか?
まるで定食屋の「日替わりランチ600円」のように、シンプルで分かりやすい顔をしていながら、裏にはオプションメニューやサービス料が山ほどついていた…そんな経験、ありませんか?
実は家づくりの世界でも、似たようなことが起きています。
この記事では、「坪単価」という一見シンプルな数字に惑わされず、家づくりの本当のコストを見極める方法を、具体例とともにわかりやすくお伝えします。
「坪単価60万円」は、完成した家の価格じゃない
まず結論からお伝えします。
「坪単価60万円で家が建ちます」と言われても、その金額で“住める状態の家”が完成するとは限りません。
なぜなら、この数字が示しているのはあくまで「建物本体の価格」だけ。
つまり、キッチン・トイレ・壁・屋根・窓といった“建物の箱”部分にかかる工事費の平均であり、それだけでは生活できる状態にはなっていないのです。
たとえるなら、エンジンだけ積んだ車の値段を聞いて「これで走れる」と思ってしまうようなもの。ガソリンもタイヤもない状態で、果たして動くでしょうか?
構造によって、そもそも“単価”が変わる
「坪単価60万円」とひと口に言っても、すべての家にそれが当てはまるわけではありません。
なぜなら家の“つくり方”によって、かかる手間や材料費が大きく異なるからです。
▼ 木造
比較的コストが抑えやすく、温かみやナチュラルな雰囲気が魅力。小規模な住宅や自然志向の人に人気。
▼ 鉄骨造
耐久性・耐震性に優れており、構造の自由度も高い。ただし、工事費・材料費ともに上がりがち。
▼ RC(鉄筋コンクリート)造
まるで要塞のような堅牢性と防音性を誇るが、工期も費用も跳ね上がる。住宅というより“建築物”のレベル。
あなたの理想とする暮らしは、どの構造に近いですか?
その答えが、予算の方向性を大きく左右します。
“広さ”の定義次第で、坪単価の見え方は操作できる
坪単価の計算は、「価格 ÷ 面積」で出しますが、ここに1つ大きな落とし穴があります。
実は「面積」の定義が会社によって違うのです。
● 延床面積で計算するケース
→ 実際に使える室内空間のみを計算対象とする
● 施工床面積で計算するケース
→ ベランダや吹き抜け、玄関ポーチまで含める
たとえば、施工床面積が広くなれば、そのぶん“坪”が増えるので、同じ価格でも坪単価は低く見えます。
つまり、「坪単価が安い!」と思っても、面積の基準が違うだけということも。
これは「内容量が少ないペットボトル飲料を“1本100円”と安く見せるテクニック」に似ています。
「建てる費用」と「暮らす費用」は別モノ
家の本体が完成しても、そこで暮らせるとは限りません。
実際には、以下のような費用が追加で発生します。
- 電気・水道・ガスの引き込み工事
- 外構(駐車場・庭・門扉)
- 照明器具・カーテン・エアコン
- 火災保険・地震保険
- 登記費用・住宅ローン事務手数料
これらはすべて、坪単価の中には含まれていないことがほとんどです。
最初の見積もりでは安く見えたのに、最終的に数百万円の追加請求が来た――そんな声も少なくありません。
注文住宅の費用は「3階建て構造」で考えよう
注文住宅にかかる費用は、大きく3つのパートに分かれます。
- 本体工事費(全体の約70〜80%)
家そのものを建てる費用 - 付帯工事費(約15〜20%)
電気・水道・外構・空調など、住める状態にするための費用 - 諸経費(約5%)
保険・税金・登記・ローン関連費など、見落とされがちな手続き費用
これらをすべて含めてはじめて、「総額でいくらかかるのか」が見えてきます。
予算は「逆算」で考えるのが正解
あなたが家づくりでまずやるべきことは、「いくらまで使ってもいいか」をハッキリさせることです。
- 手元の貯金はどれくらいあるか?
- 毎月無理なく返せるローンの金額はいくらか?
- 土地代・諸経費込みで、いくらまでなら安全か?
この「限界ライン」をあらかじめ設定しておけば、打ち合わせ中に出てくる「ちょっといい仕様」にブレずに判断できます。

見積もりは“最低3社”が鉄則
同じような家を建てる場合でも、施工会社によって金額も内訳もまったく違うのが住宅業界の現実です。
だからこそ、最低でも3社以上から見積もりを取りましょう。
- 価格の差
- 含まれている項目の違い
- オプション扱いになるものの基準
これらを比較してはじめて、「適正価格」がわかります。
家づくりにおける最大の節約術は、“情報の比較”なのです。
まとめ
- 坪単価の数字は、「住める家の総額」ではない
- 家の構造や面積の出し方によって単価の印象は変わる
- 本体価格以外に必要な工事費・手続き費用が多く存在する
- 注文住宅の費用は「本体」「付帯」「諸経費」で構成される
- 予算は「理想から積み上げる」より「現実から逆算する」が安全
- 比較見積もりを取ることで、本当のコスパが見えてくる