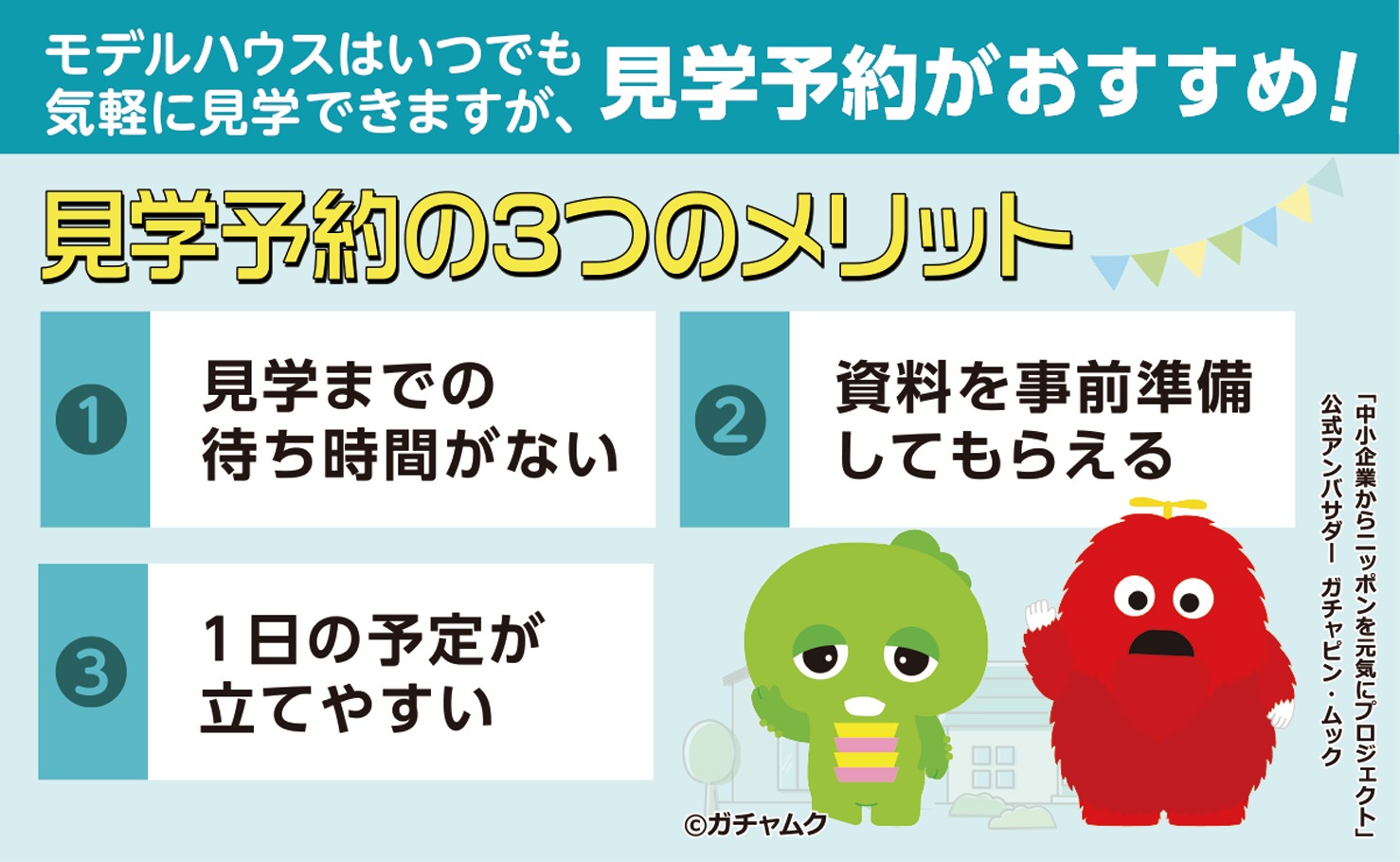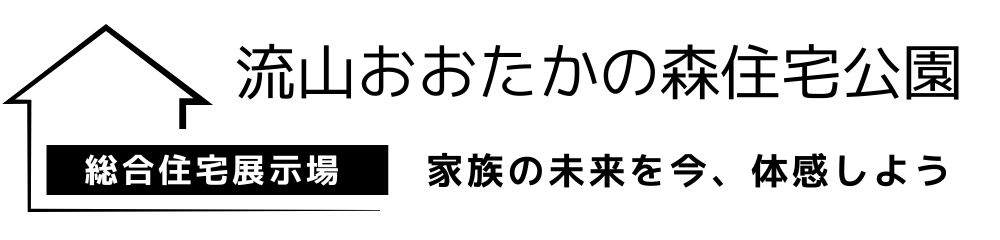この記事を読めば分かること
平屋に暮らす人たちが口を揃えて語る「人生が変わった」という言葉の真意とは何か。建築様式の選択を超えて、暮らしの哲学そのものに触れる平屋の本質を、実際の住まい手の生々しい体験談と、住宅設計の最前線で活躍するプロフェッショナルの洞察から読み解きます。あなたの家族にとって平屋が正解なのか、その判断基準から具体的な実現方法まで、すべてがこの記事で明らかになります。
はじめに
「子どもが二階で転んだ音がして、心臓が止まりそうになったことがあるんです」
35歳の母親は、二階建ての家を手放して平屋を建てた理由をこう語りました。階段という存在が、彼女の日常にどれほどの不安を与えていたか。その言葉には、単なる「便利さ」を超えた切実さがありました。
一方、28歳の若い夫婦は全く違う理由で平屋を選びました。「僕たちはミニマリスト的な暮らしに憧れていて。シンプルで無駄のない空間を求めたら、自然と平屋になったんです」
そして72歳のご夫婦は言います。「60代で家を建て直すなら、もう迷う理由がなかった。階段のない暮らしは、想像以上に心が軽くなりますよ」
年齢も家族構成も価値観も異なる人々が、なぜ同じ「平屋」という答えにたどり着くのでしょうか。
この記事では、平屋を選んだ人々のリアルなストーリーと、彼らの選択を支えた建築の知恵を紐解いていきます。住宅情報誌には載らない、本音の声と実践的な知識が、あなたの家づくりの羅針盤となるはずです。
第1章:平屋を選ぶということ―3つの世代、3つの物語
統計を見れば分かることがあります。しかし、数字では語れない真実もあります。平屋を選んだ3組の家族の物語から、その本質を探ってみましょう。
物語1:「子どもの安全」が最優先―30代夫婦の決断
松本市に住む田中さん夫婦(仮名・夫35歳、妻33歳)には、5歳と2歳の男の子がいます。以前住んでいた二階建ての賃貸アパートで、長男が階段から転落しそうになった経験が、平屋を選ぶ決定的なきっかけでした。
「あの時は本当に怖かった。階段にゲートをつけても、子どもって予想外の動きをするんです。二階建てを建てる選択肢もありましたが、『階段のない暮らし』の安心感に勝るものはないと思いました」(妻)
しかし興味深いのは、彼らが「安全性」だけで平屋を選んだわけではないという点です。
「共働きで、平日は本当にバタバタしています。洗濯機から物干し場まで階段を往復する時間すら惜しい。平屋なら動線が一直線。朝の支度時間が以前より15分短くなりました」(夫)
さらに夫婦が重視したのは、「家族が自然と顔を合わせる間取り」でした。
「リビングを通らないと各部屋に行けない設計にしたんです。子どもたちが大きくなっても、顔を見ない日がないようにしたかった。二階に子ども部屋があったら、それは難しかったと思います」(妻)
彼らにとって平屋は、「今の安全」と「未来のコミュニケーション」を同時に実現する唯一の選択だったのです。
物語2:「シンプルに暮らす」という美学―20代夫婦の選択
長野市の佐藤さん夫婦(仮名・夫28歳、妻27歳)は、子どもがいない共働き夫婦です。彼らが平屋を選んだ理由は、極めて明確でした。
「僕たち、所有物を最小限にする暮らしを大切にしているんです。服も食器も、本当に気に入ったものだけ。家も同じで、必要な空間だけで構成された家に住みたかった」(夫)
彼らが建てたのは、わずか25坪の平屋。LDK、寝室、書斎、そして土間―。それだけのシンプルな構成です。
「見学に来た友人は『狭くない?』って言いますけど、全然そんなことない。天井が高くて、窓が大きくて、視線が抜けるから、むしろ広々感じます。二階建てで35坪より、平屋の25坪の方が豊かに感じるんです」(妻)
印象的だったのは、妻が語った「掃除が楽しくなった」という言葉です。
「以前のアパートは、掃除が面倒で週に一度くらいしかしませんでした。でも今は、空間がシンプルだからササッと掃除できる。床がきれいだと気持ちいいから、毎日やるようになりました。暮らしが丁寧になったんです」
彼らにとって平屋は、ミニマルな美学を体現する器だったのです。

物語3:「人生の最終章を心地よく」―70代夫婦の終の棲家
安曇野市の山田さん夫婦(仮名・夫72歳、妻70歳)は、40年住んだ二階建ての家を解体し、同じ敷地に平屋を新築しました。
「60代後半になって、階段がきつくなりました。二階の部屋は物置状態。これなら平屋を建て直した方がいいと思ったんです」(夫)
しかし彼らの平屋は、単なる「バリアフリー住宅」ではありませんでした。広々としたウッドデッキ、開放的な土間、そして趣味の陶芸ができる小さなアトリエ空間。
「若い頃は仕事と子育てで精一杯でした。今、ようやく自分たちのための暮らしができる。この平屋は、私たちの『第二の人生』のスタートなんです」(妻)
特に気に入っているのが、庭との関係性だといいます。
「朝起きて、リビングの窓を開けるとそこはもう庭。コーヒーを持ってデッキに出て、鳥の声を聞きながら朝を迎える。二階建ての時は庭なんて年に数回しか出ませんでしたが、今は庭が生活の一部。この豊かさは、平屋でなければ得られなかった」(夫)
彼らにとって平屋は、人生の最終章を最も美しく生きるための舞台だったのです。
第2章:建築家が語る「良い平屋」と「悪い平屋」の分かれ目
3組の家族の物語から見えてきたのは、平屋には「理想の暮らし」を実現する力があるということ。しかし、すべての平屋が素晴らしいわけではありません。
30年以上住宅設計に携わってきた建築家・石川氏(仮名)に、「良い平屋」と「悪い平屋」を分ける要素について聞きました。
分かれ目1:外観は「抜き」で決まる
「平屋の外観デザインで最も多い失敗は、『何もない』か『ゴチャゴチャ』の両極端になることです」と石川氏は指摘します。
平屋は基本的に一つの大きな屋根で構成されるため、シンプルになりがち。「これではつまらない」と感じた施主が、あれこれ装飾を要望して失敗するケースが多いといいます。
「良い平屋の外観は『抜き』で決まります。全体の70%はシンプルに、残り30%に個性を集中させる。例えば、玄関周りだけに木を使う、窓のデザインに変化をつける、軒の出を一部だけ深くする。メリハリが大切なんです」
石川氏が設計した平屋の一つは、真っ白な壁に、焼杉の黒い帯が一本横に走るデザイン。極めてシンプルですが、その「一本の線」が強烈な印象を残します。
「シンプルであることは、弱いことじゃない。むしろ強い。余計なものがないからこそ、本質が際立つんです」
分かれ目2:天井は「高ければいい」わけじゃない
平屋は天井を自由に設計できることが魅力ですが、「高ければ高いほど良い」というのは誤解だと石川氏は言います。
「天井の高さは、その部屋の用途と感情によって変えるべきです。リビングのように開放感が欲しい場所は高く、寝室のように落ち着きたい場所は低く。この『高低差』が空間に表情を与えます」
ある平屋では、リビングの天井を4.5メートルまで上げた一方、寝室は2.4メートルに抑えました。
「お客様は最初『寝室が低すぎないか』と心配されましたが、完成後に『この包まれる感じが心地いい』とおっしゃいました。天井が低い部屋は、子宮にいるような安心感があるんです」
分かれ目3:光は「量」より「質」
平屋で最も難しいのが採光計画。建物の中心部が暗くなりやすいため、「とにかく窓を増やす」という失敗をする施主が多いと言います。
「大切なのは光の『量』じゃなく『質』です。直射日光がギラギラ入る部屋より、柔らかく拡散した光が満ちる部屋の方がずっと心地いい」
石川氏が多用するのは、「光の連鎖」という手法。隣の部屋からの光を室内窓で取り込み、さらに白い壁で反射させることで、家全体に柔らかい光を行き渡らせます。
「南側に大きな窓を開ければ明るい、というのは素人の発想。プロは、光がどう回り込むか、どう反射するか、一日の中でどう変化するかまで計算します」
分かれ目4:「廊下」という概念を捨てられるか
石川氏が設計する平屋には、ほとんど廊下がありません。
「廊下は『無駄な空間』の象徴です。ただ通過するためだけの場所に、建築費とメンテナンスコストをかける必要はない。すべての空間を『居場所』にするのが、良い平屋の条件です」
では、各部屋へのアクセスはどうするのか?
「リビングを『ハブ』にするんです。すべての部屋へ、リビングを経由してアクセスする。これが家族のコミュニケーションを生み、空間効率も最大化します」
ただし、プライバシーへの配慮は必須だといいます。寝室の入り口は、リビングから直接見えない位置に配置する、扉の向きを工夫するなど、細かな設計で問題を解決します。
分かれ目5:「外とのつながり」をどう設計するか
「平屋の真価は、『外とのつながり』で決まります」と石川氏は強調します。
すべての部屋が地面レベルにある平屋では、庭との関係性が暮らしの質を大きく左右します。
「ウッドデッキを単なる『オプション』と考える人がいますが、それは間違い。デッキは平屋の生命線。室内と庭をつなぐ『第三の空間』なんです」
石川氏が設計する平屋では、必ずデッキを軒下に収めます。雨の日も、真夏の日差しの強い日も使えるデッキは、季節を問わず家族の居場所になります。
「デッキで朝食を食べる、子どもがデッキで宿題をする、夫婦が夕方デッキでワインを飲む。これが『平屋的な暮らし』です。二階建てでは絶対に生まれない光景なんです」
分かれ目6:「未来の変化」を織り込めているか
最後に石川氏が強調したのが、「可変性」でした。
「10年後、20年後、家族はどうなっているか。その『未来予想図』を複数持っているかどうかが、良い平屋と悪い平屋を分けます」
子ども部屋は、将来書斎や趣味室に転用できるか。親の介護が必要になった時、寝室の配置は適切か。夫婦二人になった時、広すぎないか。
「こうしたシナリオを最低3つは想定して設計します。そうすることで、30年、40年住み続けられる家になります」
第3章:平屋を建てる前に知っておくべき「不都合な真実」
ここまで平屋の魅力を語ってきましたが、公平を期すために、平屋のデメリットも正直にお伝えします。
真実1:建築コストは「思ったより高い」
「階段がない分、安くなるんじゃないですか?」
これは最もよくある誤解だと、工務店経営者の中村氏(仮名)は言います。
「実際は逆です。同じ延床面積なら、平屋の方が2〜3割高くなるのが一般的です」
理由は単純。基礎と屋根の面積が、二階建ての約2倍になるからです。
「30坪の平屋と30坪の二階建てを比較すると、平屋の方が基礎面積も屋根面積も大きい。これが建築費を押し上げます」
ただし、中村氏は「トータルコスト」で考えるべきだと指摘します。
「平屋は屋根や外壁のメンテナンスが容易で、足場を組むコストが大幅に削減できます。30年のライフサイクルコストで見れば、差は縮まります」
真実2:土地の選択肢は「確実に狭まる」
二階建てなら建築可能な土地でも、平屋では難しいケースがあります。
「都市部の狭小地では、平屋は現実的じゃありません。30坪の家を建てるなら、最低でも60〜70坪の土地が欲しい」と中村氏。
また、プライバシーと防犯の観点から、周囲の環境も重要になります。
「平屋は全ての窓が地面レベルにあるため、隣家との距離が近いと、常にカーテンを閉めた生活になってしまう。これでは平屋の良さが活きません」
真実3:「浸水リスク」は避けられない議論
2019年の台風被害以降、平屋を検討する人から必ず聞かれるのが「浸水リスク」です。
「ハザードマップで浸水想定区域に入っている土地で平屋を建てる場合、正直にリスクを説明します。二階があれば垂直避難できますが、平屋にはそれがない」
中村氏の会社では、こうした土地では基礎を高くする、小屋裏に避難スペースを作るなどの対策を提案しているといいます。
「平屋を建てる上で、災害リスクの検討は避けて通れません。これは不都合かもしれませんが、真実です」
第4章:あなたに平屋は向いているか?―5つのチェックリスト
ここまで読んで、「自分たちに平屋が合っているのか」悩んでいる方もいるでしょう。判断材料として、5つのチェックポイントを提示します。
チェック1:「家族の距離感」をどう考えるか
平屋では、家族が物理的に近い距離で暮らします。これを「心地いい」と感じるか、「窮屈」と感じるかが、適性の大きな分かれ目です。
□ 家族が同じ空間にいることに安心感を覚える
□ 子どもの気配を常に感じられる環境が理想
□ 夫婦の時間も大切だが、孤立は避けたい
3つともチェックが入るなら、平屋の適性は高いでしょう。
チェック2:「シンプルな暮らし」に共感できるか
平屋は、基本的に「引き算の暮らし」に向いています。
□ 物を減らして、すっきり暮らしたい
□ 掃除やメンテナンスは楽な方がいい
□ 見栄より実質を重視する
これらに共感するなら、平屋のシンプルさは大きな魅力になります。
チェック3:「庭との暮らし」を楽しめるか
平屋の魅力の半分は、「外とのつながり」にあります。
□ 庭仕事や植物の世話が好き(または興味がある)
□ 外で過ごす時間に価値を感じる
□ 自然を身近に感じる暮らしに憧れる
庭に興味がない方には、平屋の真価は発揮されないかもしれません。
チェック4:「長期的視点」を持てるか
平屋は10年後、20年後の暮らしを見据えた選択です。
□ この土地に長く住むつもりである
□ 将来の家族の変化を想像している
□ ライフサイクルコストで物事を考える
短期的な視点より、長期的な視点で判断できる方に平屋は向いています。
チェック5:「本質的な価値」を見抜けるか
最後のチェックポイントは、やや抽象的です。
□ 流行より、普遍的な美しさを求める
□ 「便利さ」より「心地よさ」を優先する
□ 他人の評価より、自分たちの満足を重視する
平屋は、こうした「本質的価値」を理解できる人にこそ輝きます。
5つのうち4つ以上にチェックが入った方は、平屋の適性が非常に高いと言えるでしょう。
終章:平屋は「建築」ではなく「哲学」である
冒頭で紹介した3組の家族に、平屋に住んで半年後、改めて話を聞きました。
30代の田中さん夫婦は言います。
「子どもたちが、毎日笑顔で走り回っています。階段の心配をしなくていい暮らしが、こんなに心を軽くするとは思いませんでした」
20代の佐藤さん夫婦は言います。
「この家に住んでから、『丁寧に暮らす』ことの意味が分かりました。空間がシンプルだと、心もシンプルになる。不思議ですね」
そして70代の山田さん夫婦は言います。
「人生の最後に、最高の居場所を手に入れました。毎朝、『ああ、いい家に住んでいるな』と実感しています」
平屋という選択は、単に建物の形を選ぶことではありません。それは、どう生きるかという「哲学」を選ぶことなのです。
効率を求めるのか、余白を大切にするのか。
高さを求めるのか、広がりを求めるのか。
孤立を選ぶのか、つながりを選ぶのか。
これらの問いに対する答えが、あなたを平屋へと導くかもしれません。
階段を失うことで、私たちは何を得るのか。それは、「地に足をつけた暮らし」そのものです。空に近づくのではなく、大地に根ざす。上を目指すのではなく、横に広がる。
そんな暮らし方に共感するなら、平屋はきっとあなたの人生を豊かにしてくれるでしょう。
窓の外に広がる緑、家族の温もり、季節の移ろい。それらすべてを、同じ高さで感じながら生きる。それが平屋という生き方なのです。